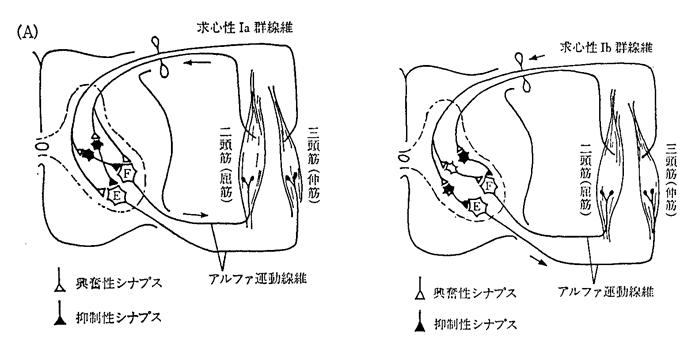最近話題の「乳酸いき値トレーニング」は、持久的トレーニングの運動強度の指針となるもので最大の持久的能力に対する%で示されます。低強度運動継続時のエネルギー源は「遊離脂肪酸(FFA)」が主要で細胞内のミトコンドリアで「有酸素的」に生成されます。そして運動強度が上昇するにつれて追加のエネルギー生産システムが必要となり「糖(筋グリコ-ゲン)」が利用されます。この際にピルビン酸が先ずつくられると考えられておりこのピルビン酸もミトコンドリアで有酸素的に処理されます。ところが運動強度が高い場合にはこのプロセスだけでは処理しきれずに「乳酸」が生成されます。このプロセスは同時並行的に進行しているので、結果的に運動強度が上がるとピルビン酸が処理しきれずに血中乳酸濃度が上昇してきます。
この血中乳酸濃度は、自覚的には「きつい」という感覚を生じさせますのでスウェーデンの著名な生理学者・ボルグ先生は、「最高に楽」から「最高にきつい」に至る6~20段階の「自覚的運動強度(ボルグスケール)」というものを提唱しています。またこの数字は運動時心拍数のおよそ1/10であることも指摘されています。
段階的に運動強度を上げてゆくと血中乳酸濃度も上昇するのですが、最大の60%強度あたりで乳酸値の増加曲線がやや急になり80%強度を超えるとさらに急激に増加するといわれています。そして80%強度を超えると乳酸をエネルギーに変換する処理が間に合わなくなりそのまま継続するのは「無理」という感覚が生じますので80%を「乳酸いき値」と定義します(血中乳酸濃度では4ミリモル/L)。
ただ腕時計型の心拍系では運動実施時の血中乳酸濃度を測ることはできませんので、80%強度と推定される心拍数を個人別に推定して表示しますが、この時問題となるのが心拍数の個人差です。基準となるものは「安静時心拍数」と「運動時心拍数」と「最高心拍数」なのですがこの「最高心拍数」が個人の年齢やトレーニング経験によって大きく異なっていることが知られています。
有名な方法は「カルボーネン法」といって最高心拍数を「220-年齢」と推定します。そして安静時心拍数と運動時心拍数との関係から、推定最高心拍数―安静時心拍数を100%として、60%強度や80%強度を計算します。40歳の方で安静時心拍数が60拍/分であれば、80%強度は((220―40:推定最高心拍数)-60:上昇キャパシティ)×80%)=96拍/分に安静時心拍数を加えた156拍/分となります。30歳で安静時心拍数が55拍/分であれば、60%強度は((220-30)-55)×60%=81拍+安静時心拍55で136拍/分です。
ですから厳密に最高心拍数を推定するためには「ビルドアップ法」といって運動強度を段階的に上げていった最高心拍数やレースでのラストスパート時の心拍数を記録したりすることで補正することが必要となります(血中乳酸を測定してもらって4ミリモル強度を推定する方法もあります)。