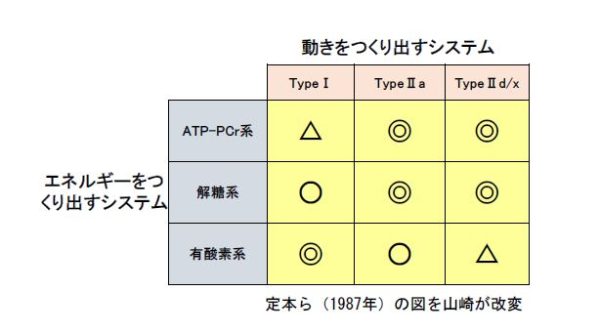スキーやスノボ、登山やトレイルランで急斜面や急峻な稜線に立った時に ”怖い”という感覚が生ずることがあります。
全く実体験がなければ「未知への恐怖」ですが、過去に失敗体験があり「自分には無理だ」と判断する場合でも、練習によりスキルが向上すれば対応できるケースもあります。生態学的心理学では「アフォーダンス」という概念があり、同じ35度の急斜面でも低速ではOKでも高速で突入したり脚に疲労感があったりすると不安が広がります。つまり同じ物理的条件でも「行動する側の状況」によって提供される(afford)情報の意味が違ってくるということで、助走に勢いがあれば「登れる階段」も勢いがなければ「登れない階段」になるということです。
深刻なのは失敗体験(大転倒など)がトラウマのようになる一種の「不安(パニック)症」に類似したケースです。実はこれは「ストレス反応」と関連していて、人類がかつてサバンナで猛獣や危険動物に遭遇した時の「闘争・逃避反応」が過剰に生じたケースです。
ハーバード大学の精神科医・レイティ医師は、人間にもともと備わっているストレス反応は、①危険に集中する、②反応を起こす、③将来のためにその経験を記憶する、こととし、情動を司る大脳基底核の扁桃体に非常スイッチが入り、視床下部⇒脳下垂体⇒副腎皮質ルートでストレスホルモン(コルチゾールなど)を放出し、これが記憶と関連する海馬に送られて前頭前野と連携して将来的に適切な反応が形成されると指摘します。問題は、過剰なストレス反応では前頭前野から扁桃体に送られる信号が乱れ、いわばフリーズしてしまう「凍結・闘争・逃避反応」が生ずること、また前頭前野と海馬に「不安(パニック)回路」が形成されてしまうことです。
この対処法には認知行動療法(CBT)があり、恐怖の記憶を中立的あるいは前向きな記憶に置き換える必要があること。対人不安のある「広場恐怖症」の治療では、誰もいない時にモール(人混みの象徴)にむって何回かダッシュさせながら不安(パニック)を引き起こさない体験を積み重ねてゆくジョンズガードによるアプローチを紹介し、「本質的には自分を振り落とした馬の背に再び乗ること」を学ぶこと、恐怖を感じても死ぬわけではないと脳に教え込むことが大切であると指摘します。
スキーであれば、急斜面を下から登って行って可能な場所から滑り降りるという「成功体験」を繰り返して「別の回路」を作ってゆくこと、また不安回路を「再活性化しない(ここは ”断崖” ではない ”スキー場の滑走斜面だ”・・大丈夫、大丈夫!)」ことも重要かもしれません。「挑戦なくして向上なし」とはいいますが「可能な挑戦」でなければ人は向上し成功しないものだと思うのです。